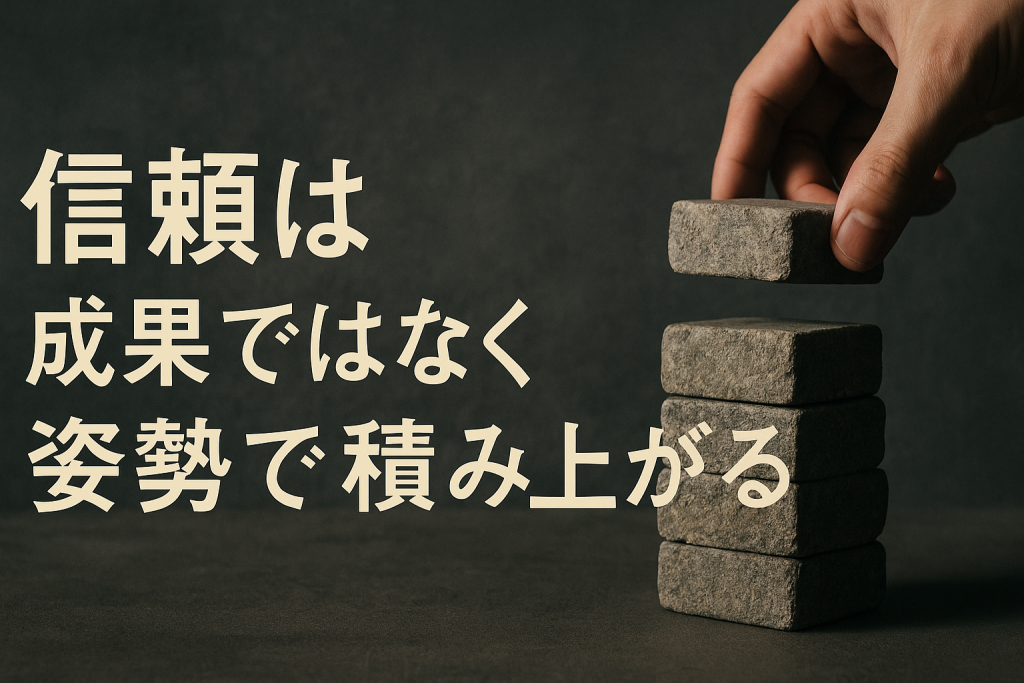はじめに|ミッションと「やりたいこと」を重ねようとしたときに起きること
とある経営者のクライアントさんとのコーチングセッションで、
会社のミッションと、社員一人ひとりの
「やりたいこと」や「成長目標」を
どう近づけていくか、という話題になりました。
組織が向かおうとしている方向と、
そこで働く人それぞれの関心や成長が、
少しずつ重なっていくこと。
そして、社員自身が
「この会社に所属していること」を
自分の成長や自己実現につながるものとして
感じられている状態。
この考え方については、
コーチとしてさまざまな立場のビジネスパーソンと
対話を重ねてきた中でも、
また、かつて自分自身が会社員だった頃、
最もパフォーマンスが高かった時期を振り返ってみても、
強く共感するところがあります。
一方で、
この考え方を実際のマネジメントや
日々のコミュニケーションに落とし込もうとすると、
「想定と違うな」と立ち止まりそうになることがあります。
たとえば、
組織が向かおうとしている方向と、社員一人ひとりの関心や成長を重ねていくきっかけとして、
「どんなことをやっていきたい?」
と問いを投げかけてみたとき。
返ってくる答えが、
自分の中で思い描いていたものと
少し違って感じられることはないでしょうか。
歯車が噛み合っていないような、ちょっとした無力感が残る。
この記事では、
こうした場面を
「質問がうまく機能しなかった」と片づけるのではなく、
その場で何が起きていたのかを、
コーチの視点から少し外側に引いて
眺めてみたいと思います。
⸻
第1章|「どんなことをやっていきたい?」という問いを投げたとき
組織の方向性と、
社員一人ひとりの関心や成長を重ねていこうとするとき、
この問いはとても自然に浮かんできます。
「どんなことをやっていきたい?」
相手を尊重しているつもりもあるし、
急かしているわけでもない。
むしろ、その人自身の考えを知りたいという
素直な関心から出てくる問いです。
実際、その場のやり取り自体は、
表面的にはきちんと成立しています。
質問が投げかけられ、
それに対して、言葉が返ってくる。
ただ、その返答を聞いた瞬間に、
管理職の側にだけ、
小さな違和感が残ることがあります。
たとえば、こんな答えです。
「まだ、そこまで考えたことがなくて……」
あるいは、
「今は、とにかく目の前の仕事を
しっかりやりたいと思っています」
または、
「会社に求められていることを
ちゃんとやっていきたいです」
どれも、
失礼でもなければ、
的外れでもありません。
むしろ、真面目で、無難で、
その場としては“正しい”答えにも聞こえます。
それでも、どこかで
歯車が噛み合っていないような感覚が残る。
「聞きたかったのは、
“あなた”がやりたいことだったんだけどな」
そんな思いが、
言葉にならないまま、
胸の内に残ることがあります。
このとき起きているのは、
答えが足りない、ということではありません。
返ってきた言葉は、
今の関係性の中で、
その人が安心して出せる”ちょうどいい答え”
だった、というだけです。
未来の話を避けた、というよりも、
未来の話をするには、
まだ少し距離があった。
あるいは、
その問いが
「考えを広げる問い」ではなく、
「評価される問い」として
受け取られていたのかもしれません。
もちろん、その社員さんが
未来のことにきちんと向き合っていない、
ということもあるかもしれません。
ここで大事なのは、
このやり取りを
「問いが悪かった」「引き出せなかった」
と整理してしまわないことだと思います。
コーチの立場からこの場面を眺めると、
ここで表に出ているのは、
その人の意欲や主体性ではなく、
今、この関係性の中で
どこまでの話が”安全”と感じられているか
という情報です。
問いは、
答えを引き出すために投げられたけれど、
実際には、
関係性の現在地を
そのまま映し出している。
だからこそ、
あの「歯車が噛み合っていない感じ」は、
何かが足りなかったサインではなく、
次にどこを扱えばいいのかを
教えてくれている感覚
なのかもしれません。
⸻
第2章|対話を少し外側から眺めてみると
対話の渦中にいるとき、
管理職の意識はどうしても
「何を聞くか」「どう返すか」に向きがちです。
けれど、
あの歯車が噛み合っていないような感覚が残った場面を、
少しだけ外側から眺めてみると、
違うものが見えてきます。
ぼくが、歯車が噛み合っていないような感覚がある時に
注目するのは、
返ってきた答えの中身そのものではないことが多いです。
どちらかというと
安心して回答できていない状態に、
注意が向けられます。
こうした要素は、
本人が意識してコントロールしているというよりも、
その関係性の中で自然に立ち上がってくるもの
であることがほとんどです。
たとえば、
未来の話になった瞬間に、
言葉が少し抽象的になる。
主語が「自分」から
「会社」や「求められていること」に
すっと移る。
あるいは、
考えながら話しているというより、
安全そうな言葉を
選びにいっているように感じられる。
それは、
考えていないからでも、
やる気がないからでもありません。
その距離感では、
そこまで踏み込まなくてもいい
と、身体が判断している状態
とも言えます。
また、
問いを投げた側が
評価する立場や、
何かを決める立場にあるとき、
本人にその意図がなくても、
場はわずかに緊張を帯びます。
このとき、問いは
「考えを広げるためのもの」ではなく、
「どう答えるのが無難か」を
探らせてしまうことがあります。
人は、
安心していない場で
わざわざ不確かな未来の話を
深く掘り下げようとはしません。
だから、
対話が浅くなったり、
言葉が無難になったりするのは、
個人の資質や姿勢の問題というよりも、
場と関係性がそうさせている
と捉えることができます。
ここで大切なのは、
この場面を通して、
今はどんな話題までなら安心して扱えるのか
どんな前提があれば、もう一歩踏み込めそうなのか
そうした情報が
静かに立ち上がっている、
という点に目を向けることです。
対話を少し外側から眺めると、
見えてくるのは
関係性の状態。
そして、
その状態が見えてきたとき、
次にどんな関わり方を選ぶか。
その選択肢が、
少しだけ増えていきます。
⸻
第3章|「やりたいこと」は、引き出すものなのか
ここまで見てきたように、
「どんなことをやっていきたい?」という問いが
想定どおりに展開しない場面では、
問いそのものよりも、
その場の関係性や状態が
大きく影響していることがあります。
このとき、
管理職や関わる側が
無意識に考えてしまうのが、
「どうすれば、やりたいことを引き出せるのだろうか」
という問いです。
けれど、
コーチの立場から対話を見ていると、
少し違う見え方をすることがあります。
「やりたいこと」は、
質問によって
どこかから取り出すもの、
というよりも、
状態が整った結果として、
自然に輪郭を持ってくるもの
のように見えるからです。
安心して話せているとき、
評価される心配が薄れているとき、
今すぐ決めなくていいと
身体が感じているとき。
そうした状態の中では、
本人もまだ言葉にしきれていなかった関心や違和感が、
会話の途中で、
ぽつりと現れることがあります。
それは、
最初から明確な形をしているとは限りません。
• なんとなく気になっていること
• 最近、少し引っかかっている出来事
• 得意とも不得意とも言い切れない感覚
そうした断片が、
対話の中で少しずつ並び、
あとから振り返ったときに
「あれが、やりたいことの芽だったのかもしれない」
と見えてくる。
こう言った場面での
「やりたいことを聞く」という行為は、
答えを得るためというよりも、
その人の関心に、
ご本人が、そして組織が
踏み込む準備が出来ているかどうかを
確かめる行為である
と感じます。
だからこそ、
問いに対して
はっきりした答えが返ってこなかったとしても、
それは、
まだ言葉にする段階ではなかった。
あるいは、
その問いが向けられた文脈では、
そこまで踏み込む必要を
感じていなかった。
ただ、それだけのことです。
「やりたいこと」を
無理に言語化させようとすると、
対話はどこかで窮屈になります。
一方で、
今はどんな話題なら
安心して扱えるのか。
どんな前提があれば、
もう一歩、内側の話に近づけそうなのか。
そうした状態に目を向けていると、
結果として、
その人自身の言葉で語られる
関心や方向性が、
あとから立ち上がってくることがあります。
問いは、
答えを引き出すための
道具というよりも、
状態を確かめ、
関係性と文脈が
そこに踏み込めるかどうかを見極めるためのもの
そう捉えてみると、
「やりたいことを聞く」という行為の意味も、
少し違って見えてくるかもしれません。
⸻
第4章|関係性を少し調整すると、対話の質が変わる
ここまで見てきたように、
「やりたいこと」をめぐる対話が
思ったように進まない場面では、
問いの内容そのものよりも、
その場にある関係性や前提が
大きく影響しています。
では、
その関係性を「変える」必要があるのかというと、
必ずしもそうではありません。
多くの場合に起きているのは、
少しズレた前提のまま会話が進んでいる
という状態です。
たとえば、
• 今は決める場なのか、考える場なのか
• 評価が行われる文脈なのか、探索の文脈なのか
• 会社の話をしているのか、個人の話をしているのか
こうした前提が、
共有されないまま混ざっていると、
対話はどこか噛み合わなくなります。
このとき、
大きな働きかけをしなくても、
関係性を「少しだけ調整する」ことで、
対話の質が変わることがあります。
たとえば、
今すぐ結論を出す場ではないことを
あらかじめ共有する。
今日の話が、
評価や配置に直結するものではないと
言葉にしておく。
あるいは、
「正解を出す話ではなく、
考えを並べる時間にしたい」
と、場の目的を揃える。
それだけで、
相手の話し方や、
言葉の選び方が
少し変わることがあります。
これは、
相手を変えたというよりも、
安心して話してもいい範囲が少し広がった
という変化です。
関係性の調整とは、今、
どこまでの話なら扱えるのか。
どんな前提が共有されているのか。
その輪郭を、
ほんの少し明確にすることです。
そうして場が整うと、
それまで語られなかった関心や違和感が、
自然と話題に上がることがあります。
「やりたいことを聞こう」と
力を入れなくても、
その人の言葉で、
少しずつ方向性が語られ始める。
その変化は、
劇的ではありません。
けれど、
対話の質としては、
確かに違うものになります。
関係性を扱うというのは、
相手の内面に踏み込むことではなく、
対話が行われている”場”を
丁寧に整えること
そう考えると、
管理職が担っている役割も、
少し違って見えてくるかもしれません。
⸻
第5章|問いが投げられる前から、対話は始まっている
ここまで振り返ってみると、
「やりたいことを聞く」という問いそのものが、
対話の成否を決めていたわけではないことが
見えてきます。
問いが投げられる前に、
すでに場には空気があり、
関係性があり、
共有されている前提があります。
その状態の上に、
問いが置かれる。
だから、
同じ問いであっても、
返ってくる言葉や、
対話の手応えは変わってきます。
歯車が噛み合っていないように感じたとき、
その原因を
「問いの選び方」や
「聞き方」に求めたくなるのは、
とても自然なことです。
けれど、
その違和感はもっと手前で
すでに形を持っていたようにも感じられます。
今は、
決める場なのか。
考える場なのか。
評価が関係する文脈なのか。
探索が許されている文脈なのか。
会社の話なのか。
個人の話なのか。
そうした前提が、
言葉にされないまま混ざっていると、
問いは自然と
「どう答えるのが無難か」を
探らせるものになります。
それは、
誰かが間違えたからではありません。
その場が、
そうした対話を生みやすい状態だった、
というだけです。
対話を扱うというのは、
相手の内面に踏み込むことでも、
正しい問いを探し当てることでもありません。
問いが投げられる前に、
どんな場が出来ているかに目を向けてみる
どこまでの話が扱われそうか。
どんな前提が共有されていそうか。
今は、どんな温度の時間なのか。
そこに意識が向くと、
問いの役割も
少し違って見えてきます。
問いは、
何かを引き出すためのスイッチというより、
すでに始まっている対話の流れを
そっと確かめるためのもの。
そう考えると、
思ったような答えが返ってこなかった場面も、
違う意味を持ち始めます。
それは、
失敗でも、停滞でもなく、
今の関係性や場の状態が
そのまま現れた一瞬
だったのかもしれません。
問いが投げられる前から、
対話は始まっている。
そう捉えてみると、
管理職として、
あるいは誰かと関わる立場として、
自分が向き合う対象も、
少し静かに、
広がっていくように感じられます。
⸻
相手の回答がつくる、
あなたの中の感覚には、
どんな意味があるでしょうか。