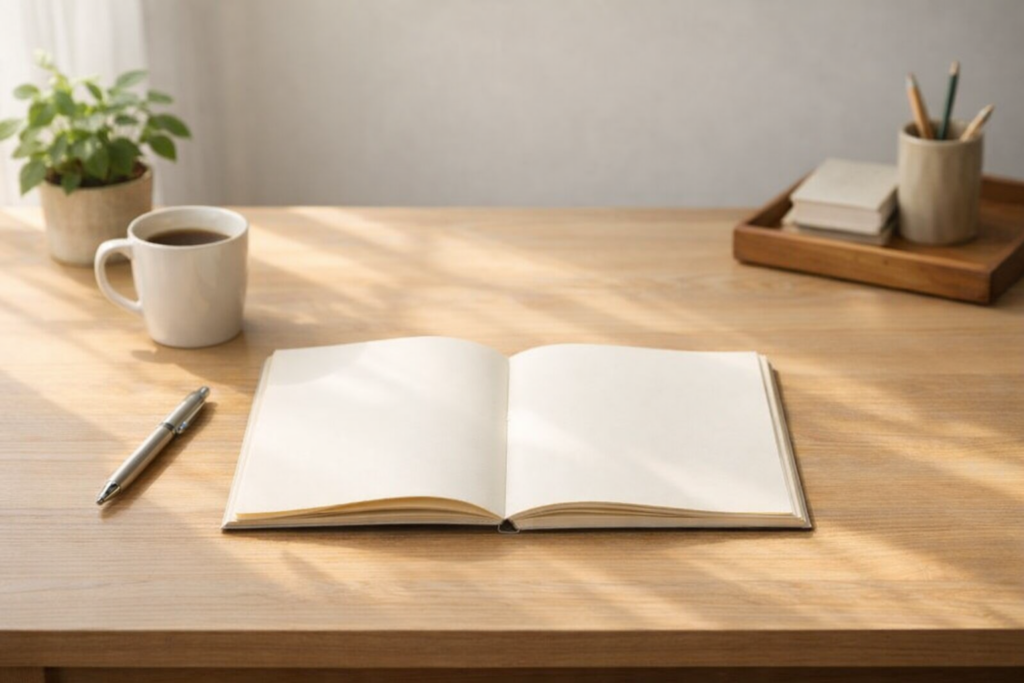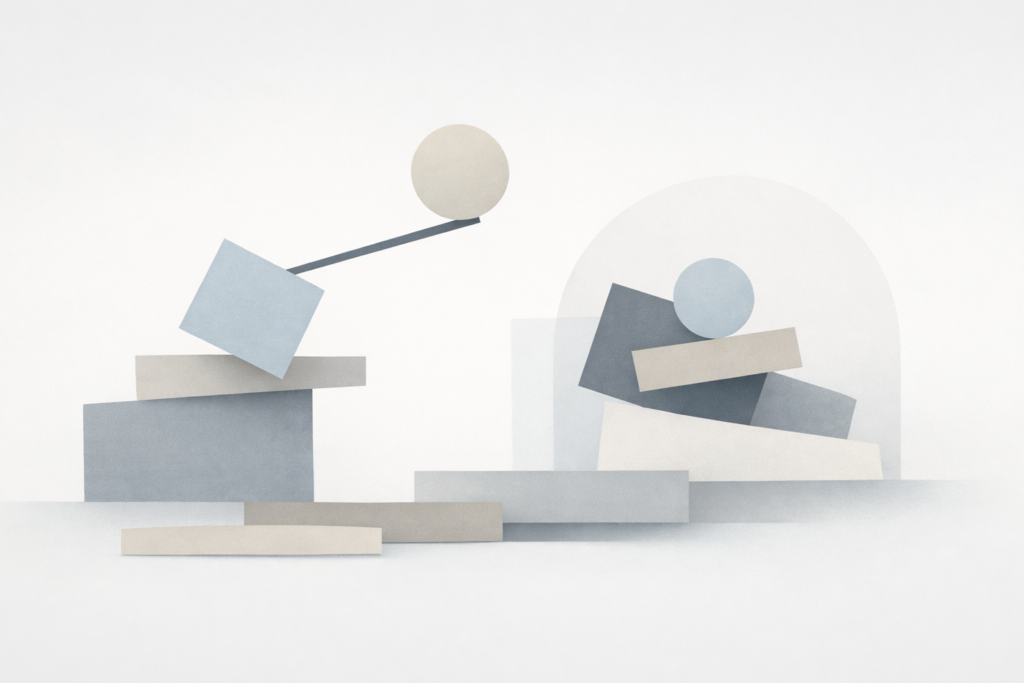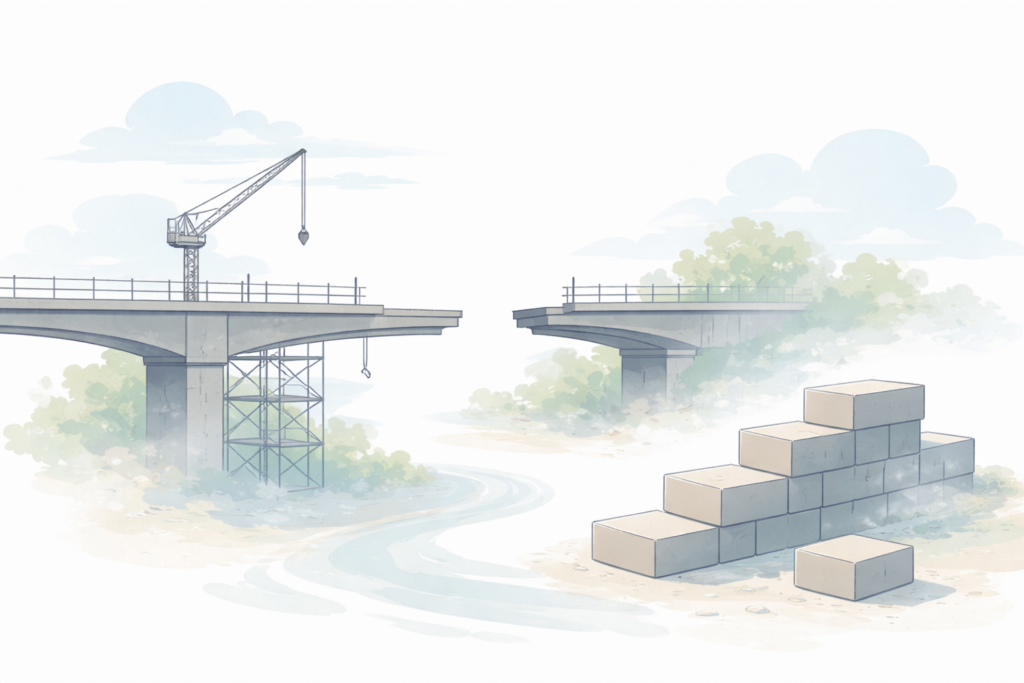「期待されている」自分に残る、説明しづらい違和感
ぼくはビジネスコーチとして、
これまで多くの方のキャリアや仕事の節目に立ち会ってきました。
今日は、その中でも、
とある企業の経営企画室長をされているクライアントさんとの対話
をきっかけに感じたことを、少し整理してみたいと思います。
あくまで一人の方との対話がきっかけではありますが、
同じような立場にある方には、
どこか重なる感覚があるかもしれません。
⸻
彼女との対話からは、
仕事はきちんと回っている。
判断に迷うことはあっても、手が止まることはない。
成果も一定水準では出せていることが伝わってきます。
むしろ組織の中では、
「安心して任せられる人」
「最後まできちんとやり切る人」
として見られていることの方が多いように見えます。
上層部からの評価も、決して低くありません。
ただ最近、
向けられている視線の質が、
少し変わってきたように感じている、ことも伝わってきます。
「もっと任せたい」というより、
「そろそろ殻を破ってほしい」
「これまでの延長ではない動きを見せてほしい」
──そんな、はっきりとは言葉にされない期待があるようです。
明確な指示があったわけではありません。
何かを求められていると、言葉で伝えられたわけでもありません。
それでも、
「次の段階に進むこと」を前提に見られているような感覚
が、どこかに残っている。
一方で、彼女自身の内側を見てみると、
不安で動けなくなっているわけでも、
自信を失っているわけでもないように感じられます。
やろうと思えば、
今のやり方で仕事は進められる。
迷いを抱えながらでも、
現実的な判断はできてしまう。
ただ、そこにひとつだけ、
うまく言葉にできない引っかかりが残っている。
どう変化していけばいいのか。
どう成長していけばいいのか。
上層部が期待している「殻を破る」という状態が、
自分の中で、まだ具体的なイメージとして結びきっていない。
そのため、
動けないというよりも、
期待の意味が、まだ十分に腑に落ちていない
そんな感覚に近いのかもしれません。
この違和感は、
「能力が足りないから」と単純に言い切れるものでも、
「やる気が下がったから」と片づけられるものでもなさそうです。
むしろ、
これまで誠実に役割を果たし、
周囲の期待に応えてきた人だからこそ、
ふと立ち止まる形で現れる、
とても静かで、説明しづらい感覚なのだと、
ぼくは感じています。
⸻
第1章|迷っているのに、仕事はちゃんと進んでしまう
迷っていないわけではありません。
ただ、その迷いは、仕事を止めてしまう種類のものではないようです。
彼女との対話からは、判断が必要な場面では判断できていることが伝わってきます。
会議では論点を整理し、現実的な落としどころを示すこともできる。
難しい調整役も、必要であれば引き受けられる。
だからこそ、日常業務は回っていきます。
多少の違和感を抱えながらでも、仕事は前に進んでしまう。
ここに、この違和感の扱いづらさがあるのかもしれません。
⸻
問題は「できない」ことではない
変化できない理由は、
しばしば「準備不足」や「能力不足」として語られます。
ただ、彼女の話を聞いていると、少し違う構図にも見えてきます。
これまで積み上げてきた経験がある。
現場も、組織全体も、どちらも見えている。
実行力も、周囲からの信頼も、すでにある。
少なくとも、「能力が足りないから動けない」と単純に言い切れる感じではありません。
それでも大きく踏み出す感覚がつかみにくいとしたら、
「次にどう変化すればいいのか」という像が、まだ自分の中で結びきっていない。
そんな状態に近いのかもしれません。
⸻
自己評価が低いというより、「慎重さ」が前に出ることがある
ご本人は、自分を過小評価しているつもりはないようです。
むしろ、現実を冷静に見ているだけだと感じている。
ただ、その冷静さはときに、
• どこまで踏み込めばいいのか
• どの変化が“やりすぎ”にならないのか
を慎重に見極めようとする姿勢につながっていきます。
その結果として、
大胆な一手よりも、確実に成立する一手を選び続けてきた。
そんな流れがあっても不思議ではありません。
そしてこれは弱さというより、
これまで信頼を積み上げてきた理由でもあるのだと思います。
ただ同時に、
役割が切り替わる局面では、その慎重さがブレーキとして働くこともあります。
(本人の意思というより、習慣や責任感の形で出てくることが多い印象です。)
⸻
「止まっている」のではなく、「まだ定義できていない」
この状態を「立ち止まっている」と表現すると、少し違和感が残ります。
実際には止まっていません。
今の役割の中では、きちんと前に進んでいます。
ただ、
• どう変化していけばいいのか
• どんな成長を求められているのか
が、まだ自分の言葉として定義しきれていない。
だから、行動できないというよりも、
変化の方向が、まだ像として結ばれていない。
そんな状態に近いのではないでしょうか。
⸻
迷いながら進めてしまう人に起きやすいこと
この違和感は、
仕事がうまくいっていないときに出るものとは、少し質が違うように感じます。
むしろ、
• 周囲の期待に応えてきた人
• 組織の中核として機能してきた人
• 「任せれば大丈夫」と言われてきた人
そういう人ほど、静かに抱えやすい。
迷いながらでも進めてしまうからこそ、
どこで引っかかっているのかが、外からは見えにくい。
そして本人も、
「この程度の違和感で立ち止まっていいのだろうか」
と、自分にブレーキをかけてしまうことがあります。
⸻
この章のまとめ
第1章で扱っているのは、「停滞」そのものではありません。
役割の切り替えを前にして、
変化の定義が、まだ自分の中に定まりきっていない状態。
ぼくには、まずはそう見えています。
次の章では、
なぜ未来は描けているのに、
その未来に向かう“動き方”だけが見えてこないのか。
その構造を、もう一段深く見ていきます。
⸻
第2章|未来は描けているのに、変化の仕方だけが見えてこない
不思議なことに、
彼女との対話を通して感じるのは、
未来そのものが見えていないわけではない、という点です。
5年後、組織がどうなっていたらいいか。
どんな状態であれば「うまくいっている」と言えそうか。
その輪郭は、かなり具体的です。
売上や利益といった数字の話だけではありません。
ブランドのあり方。
現場の空気。
そこで働く人たちの表情。
そうしたものを含めた
「こうありたい会社像」は、すでに言葉になっています。
⸻
見えていないのは「未来」ではない
それでも、なぜ動きづらさが残るのか。
ここで立ち止まって考えてみると、
少し違う見え方が浮かんできます。
見えていないのは未来そのものではなく、
「そこに向かう自分自身の変化の形」
なのかもしれません。
今の役割の延長で、
何を改善すればいいかは想像できる。
今の立場で、
何を最適化すればいいかも分かっている。
けれど、
• 今の役割を、どこまで越えていいのか
• 自分は、どんな存在へと変わっていく必要があるのか
そのあたりは、まだはっきりとした像になっていない。
そんな状態にも見えます。
⸻
「やるべきこと」は分かる。でも、しっくりこない
多くの管理職の方と話していると、
共通して出てくるのが
「やるべきこと」のリストです。
仕組みを整える。
数字を可視化する。
人を育てる。
部門間の連携を強める。
どれも間違いではありません。
実際、どれも必要なことです。
それでも、
「これでいいはずなのに、どこか引っかかる」
そんな感覚が残ることがあります。
それは、
それらが これまでの自分の延長線上にある動き
だからなのかもしれません。
上層部が期待しているのは、
改善の積み重ねそのものではなく、
見方や立ち位置が一段変わること
なのではないか。
そんな可能性も感じられます。
⸻
期待が、まだ腑に落ちきらない理由
「殻を破ってほしい」
「次の段階に進んでほしい」
そう言われている“気がする”。
けれど、その中身がはっきりしない。
そのため、
期待に応えられないというよりも、
期待の意味を、まだ自分の中で翻訳しきれていない
そんな状態になることがあります。
これは、理解力が足りないからではなさそうです。
むしろ、
組織の文脈や力学をよく分かっている人ほど、
安易な解釈を避けようとします。
その慎重さが、
「分かったつもりで動く」ことを、
無意識のうちに止めているのかもしれません。
⸻
未来像と行動の間にある「役割のズレ」
ここで起きているのは、
意欲と能力のズレ、ではありません。
未来像と、今担っている役割とのズレ
と捉えたほうが近いように思います。
今の役割は、
• 整える
• 回す
• 安定させる
ことを前提に設計されています。
一方で、
彼女が描いている未来は、
• 問いを立てる
• 前提を揺さぶる
• 方向性を示す
ことを必要としている。
このズレがある限り、
「何をすればいいか」は分かっても、
「どう変わればいいか」が見えにくい。
そう感じるのも、自然なことです。
⸻
動けないのではなく、「移行期にいる」
だからこれは、
決断力が足りない状態でも、
覚悟が足りない状態でもありません。
役割を移行している途中にいる
と考えるほうが、しっくりきます。
これまでの自分を完全には手放せない。
けれど、そのままでは足りないとも感じている。
その間に立たされたとき、
人は一度、動きがゆっくりになることがあります。
それは失速ではありません。
視点を切り替えるための減速
と捉えることもできそうです。
⸻
この章のまとめ
第2章で扱っているのは、
「なぜ動けないのか」という問いではありません。
なぜ、変化の像だけが結びにくいのか
という問いです。
次の章では、
このズレを生み出している背景としての
「役割の慣性」について、
もう少し踏み込んで見ていきます。
⸻
第3章|優秀な管理職がハマりやすい「役割の慣性」
ここまで見てきた違和感は、
個人の性格や意志の問題として片づけられるものではなさそうです。
ぼくがクライアントさんとの対話を通して感じるのは、
むしろ多くの場合、
役割そのものが持つ「慣性」 から生まれているのではないか、
という点です。
⸻
役割は、成果を出すほど人を固定されていく
管理職として成果を出してきた人には、
いくつか共通する特徴があります。
• 周囲の期待を正確に読み取れる
• 組織の空気を乱さずに前に進められる
• 「今、何をすべきか」を外さない
これらは、簡単に身につく力ではありません。
だからこそ評価され、任されてきたのだと思います。
ただ、その積み重ねの中で、
ひとつ見落とされがちな点があります。
役割は、成果を出せば出すほど、
「うまくいったやり方=正解の型」 を
少しずつ強化していく、ということです。
⸻
「うまくやってきたやり方」から、離れにくくなる
これまで評価されてきた行動を振り返ると、
そこには共通点が見えてきます。
• 周囲と合意形成をとる
• 現実的な落としどころを探す
• 波風を立てずに前に進める
どれも、組織を安定させるうえで欠かせない動きです。
ただ、次の段階で求められているのが、
• 前提そのものを問い直すこと
• あえて未整理な問いを差し出すこと
• まだ答えのない方向性を示すこと
だとしたら、
これまでと同じやり方では、
どこか噛み合わなくなってくることがあります。
⸻
慣性は、怠慢ではなく「誠実さ」から生まれる
「役割の慣性」という言葉を使うと、
惰性や保身のような印象を持たれるかもしれません。
けれど、実際の対話では、
むしろ逆の印象を受けることが多いです。
• 組織を混乱させたくない
• 周囲の努力を無駄にしたくない
• 軽率な判断をしたくない
そうした 誠実さ があるからこそ、
人は慎重になります。
ですから、ここで起きているのは、
「変われない人」の話ではありません。
変化に対して、きちんと責任を感じている人
に起きやすい現象だと、ぼくは見ています。
⸻
役割が変わるとき、いちばん難しいのは「やめ方」
新しい役割に移るとき、
人はつい「何を始めるか」に意識が向きがちです。
けれど実際には、
何をやめるか のほうが難しい場合が多くあります。
たとえば、
• すべてを自分で把握しようとすること
• 正解を出そうとする姿勢
• その場をうまく収める役回り
これらは、
これまで自分を支えてきた大切な武器でもあります。
だからこそ、簡単には手放せません。
ただ、役割が変わる局面では、
それらが 次の役割への入り口を、結果として塞いでしまう
こともあります。
⸻
「殻を破る」とは、性格を変えることではない
上層部から語られる
「殻を破ってほしい」という期待は、
大胆になれ、強く主張しろ、という意味ではないことが多いです。
ぼくの経験では、それはむしろ、
• 視点の置きどころを変えること
• 自分が立つ位置を、半歩ずらしてみること
• これまでとは違う問いを引き受けること
を指しているように感じます。
つまりこれは、
性格の問題というより、
役割の置きどころの問題 なのだと思います。
⸻
この章のまとめ
第3章で見てきたのは、
なぜ慎重で誠実な人ほど、
次の一歩が見えにくくなることがあるのか、という構造です。
それは、怠慢でも、勇気不足でもありません。
役割に誠実であろうとするほど、
その役割から離れるのが難しくなる。
次の章では、
この慣性を無理に断ち切ろうとするのではなく、
どう扱っていけばいいのか。
「いきなり変わらなくていい」という前提で、
次の進み方を整理していきます。
⸻
第4章|それは停滞ではなく、「役割が切り替わり始めている」合図
ここまで読み進めてきて、
「それでも、やはり止まっているように感じる」
そんな感想を持たれた方もいるかもしれません。
仕事は回っている。
評価も大きく落ちてはいない。
未来像も、ある程度は描けている。
それなのに、
次の動きが、どうにもはっきりしない。
この状態を「停滞」と呼んでしまうと、
どうしてもネガティブな印象になります。
けれど、
ぼくが対話の中で感じているのは、
ここで起きているのは「止まっていること」ではなさそうだ
ということです。
⸻
見えている世界が、すでに変わり始めている
これまでと決定的に違ってきているのは、
「見えている範囲」そのものです。
以前は、
• どう改善すれば、うまく回るのか
• どこを整えれば、成果が出るのか
といった問いが、自然と立ち上がっていました。
ところが最近は、
• この組織は、どこに向かおうとしているのか
• 今の延長線で、本当に持続するのか
• 何を問い直す必要があるのか
といった、
もう一段、上流の問い が目に入ってくるようになります。
これは、能力が上がったから、というよりも、
役割の射程が変わり始めている
そう捉えたほうがしっくりくる場面が多いように思います。
⸻
今の役割では、扱いきれない問いが増えてくる
これまで担ってきた役割は、
• 正解を探すこと
• 最適解を選ぶこと
• 現実的に実装すること
を前提に設計されていました。
ところが今、
目の前に現れているのは、
• まだ正解が存在しない問い
• 組織の前提そのものを揺らす問い
• 答えを急ぐほど、ズレてしまう問い
です。
当然、
これまでのやり方では扱いにくく感じます。
だから違和感が生まれる。
けれどそれは、
能力の限界にぶつかっているからではありません。
役割の射程が、すでに広がり始めている
そのサインとして現れている可能性があります。
⸻
「前と同じやり方で進めない」ことは、後退ではない
この段階で、
多くの人が自分を責めてしまいます。
• 以前のような手応えがない
• 進んでいる実感が薄い
• 判断に時間がかかるようになった
そうした変化を、
「成長が止まった」と捉えてしまうことがあります。
ただ、別の見方もできそうです。
地図のスケールが変わっている
と考えると、どうでしょうか。
地図が拡大されれば、
一歩一歩は小さく見えます。
進んでいないように感じるのは、
扱っている領域が広くなっているから。
そう捉えることもできるのではないでしょうか。
⸻
役割が切り替わるとき、人は一度「鈍く」なる
役割が切り替わる局面では、
多くの人が一時的に動きづらさを感じます。
判断に時間がかかる。
即答を避けるようになる。
言葉を選ぶ時間が増える。
これは、
感覚が鈍くなったわけではありません。
これまでとは違う感覚を使い始めている
その途中段階として起きていることが多いのです。
新しい役割に必要な感覚は、
最初からはっきりしているものではありません。
だから一時的に、
「うまく動けていない」
そんなふうに感じてしまうことがあります。
⸻
この章のまとめ
第4章でお伝えしたかったのは、
次の点です。
今感じている違和感は、
止まっている証拠ではない
ということ。
それは、
役割が切り替わり始めた人にだけ現れる、
ごく自然なサインでもあります。
次の章では、
この移行期にいるとき、
いきなり行動を変えなくていい理由と、
まず整えておきたいものについて、
もう少し具体的に整理していきます。
⸻
第5章|いきなり行動を変えなくていい。まず整えるのは「問い」
ここまで読み進めてくると、
「では、何から変えればいいのだろうか」
そんな疑問が浮かんでくるかもしれません。
役割が切り替わり始めている。
違和感は、決して悪いものではない。
そこまでは、なんとなく腑に落ちてきた。
それでも、
日々の現実は待ってくれません。
だからこそ、
ここでひとつ、あらかじめ共有しておきたいことがあります。
この段階で、いきなり行動を変えなくてもいい。
ぼくは、そう考えています。
⸻
行動を急ぐほど、ズレが大きくなることがある
変化の気配を感じたとき、
人はつい「何かをしなければ」と思いがちです。
新しい施策を打つ。
役割を広げる。
思い切った提案をしてみる。
もちろん、それ自体が悪いわけではありません。
ただ、
変化の輪郭がまだはっきりしていない段階での行動は、
かえって違和感を強めてしまうこともあります。
それは、
問いが整っていないまま、答えを出そうとする状態
に近いからかもしれません。
⸻
先に整えたいのは、「問いの置きどころ」
この移行期において、
まず必要になるのは、
行動計画よりも「問い」の整理です。
たとえば、こんな問いがあります。
• 今の役割の中で、私は何を最適化しているのか
• それは、これからの会社にとっても最適なのか
• 私が「踏み込まないことで守っているもの」は何だろうか
• 逆に、まだ引き受けていない問いは何だろうか
これらは、
すぐに答えが出る問いではないかもしれません。
けれど、
この問いを持ち続けることで、
「次にどこへ動くか」ではなく、
「どこに立てばいいのか」 が、
少しずつ見えてくることがあります。
⸻
問いが変わると、行動の意味も変わる
問いが変わると、
同じ行動でも、その意味合いが変わってきます。
たとえば、
• 会議で発言する
• 数字を見直す
• 人に問いかける
といった行動も、
「うまく回すため」ではなく、
「前提を見直すため」
という意味を帯びるようになります。
行動の数を増やす必要はありません。
行動の「質」が変わる のです。
⸻
「殻を破る」とは、劇的な変化のことではない
上層部から使われがちな
「殻を破ってほしい」という言葉は、
少し誤解を生みやすい表現でもあります。
大胆な決断をすること。
強く主張すること。
誰かを説得すること。
必ずしも、そういうことを指しているわけではありません。
ぼくの経験では、多くの場合、
• 問いのレベルを一段上げること
• これまで扱ってこなかったテーマを引き受けること
• 答えのない話を、場に出してみること
といった変化を意味しています。
つまり、
行動よりも先に、立ち位置が変わる
ということなのだと思います。
⸻
違和感を消そうとしない人から、次の流れは始まる
最後に、これだけはお伝えしておきたいことがあります。
違和感を、急いで消そうとしなくていい。
無理に納得しようとしなくてもいい。
その違和感は、
これまでの自分を否定するものではありません。
次の役割を引き受ける準備が、すでに始まっている
そのサインとして現れている可能性があります。
問いを持ち続けること。
すぐに答えを出さないこと。
それ自体が、
すでに変化の一部になっている。
ぼくは、そう感じています。
⸻
まとめ
今の仕事に、どこかハマりきらない感覚があるとしたら、
それは「足りない」からではないのかもしれません。
見えている世界が変わり、
引き受ける役割が変わり始めている
その途中にいるだけ、という可能性もあります。
その移行期にいるとき、
いちばん大切なのは、
正しく動こうとすることではありません。
正しい問いを、手放さずに持ち続けること。