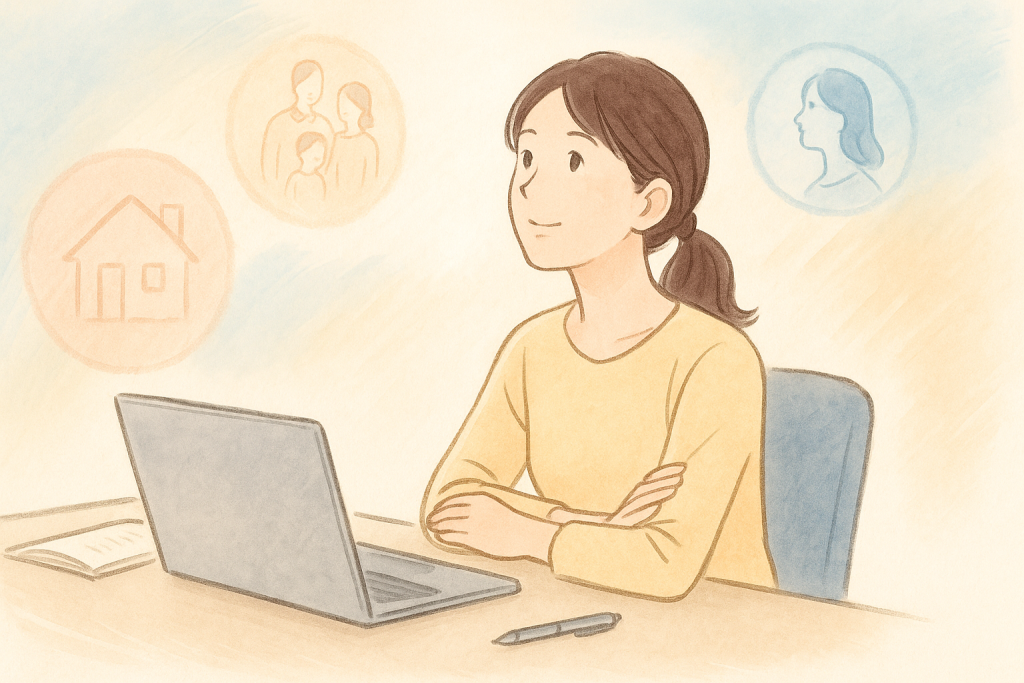最近、とある働くママのクライアントさんと
コーチングセッションで話したことが、ちょっと心に残っています。
何事にもきっちり向き合うタイプの、とても素敵な方なのですが、
“今日をこなす”ことで精一杯になっていて、
本当にやりたい仕事に向かえている感覚が持てていない——
どうやら、そんな日々が続いているようでした。
きっと、この感覚って
多くの方にとって共通するものがあるんじゃないかと思います。
仕事、家庭、子育て。
どれも手を抜きたくないからこそ、
未来のことを考える余裕がなかなかつくれない。
でも実は、
未来を描くことは、“今を整える力”になるんです。
未来を見渡せるだけで、
いまの気持ちに少しゆとりが生まれたり、
日々の選択が軽くなったりすることがあります。
この記事では、
忙しい働くママでも無理なく未来を描き直せる
「現在 → 5年後 → 1年後」の棚卸しの方法と、
本当にやりたい仕事に向き合うためのヒントをまとめました。
家族もキャリアも大事にしたいあなたへ。
一緒に“5年後の私”を描き直す時間を過ごしていきましょう。
⸻
序章|気づいたら“今日をこなすだけの毎日”になっていませんか?
気づけば毎日、仕事と家庭の予定をつないで走り続けている。
日中は会議や業務対応であっという間に時間が過ぎ、
気がつけばもう夕方。
家のことは家のことで、やるべきことはたくさんある。
子どもの学校連絡の確認、夕飯の支度、翌日の準備。
ようやく一息つけた頃には、もう寝る時間になっている。
こんなふうに「今日を回すだけ」で終わる日が続くと、
ふと 「この先、私はどうしたいんだろう?」 と
立ち止まる余裕さえなくなってしまう。
仕事は嫌いじゃない。むしろ好き。
家族も大事で、子どもたちとの時間も欠かせない。
毎日は忙しいけれど、どこか「充実している」感覚もある。
ただ、その“充実”の影で、
未来の自分を置き去りにしてしまう怖さ が
じわっと広がっていることに気付く瞬間がある。
今日をこなすだけで手一杯のとき、
「本当にこの働き方でいいのか?」
「5年後の私は、どんな時間を生きていたいのか?」
そんな問いが、心の奥で静かに聞こえてくる。
あなたは怠けているわけじゃない。
むしろ、誰よりもがんばっている。
だからこそ、忙しさに飲み込まれる前に、
ほんの少しだけ“未来の自分”へ意識を向ける時間が必要になる。
忙しい毎日でも、未来はいつからでも描き直せます。
今回の記事では、その具体的なステップを整理していきましょう。
⸻
第1章|忙しさが続くと「この先の私」が曇っていく理由
未来のことを考えたい気持ちはあるのに、
なぜか“この先の自分”の姿をイメージしようとするとぼんやりしてしまう——。
忙しさに追われる日々が続くと、
未来を描くための思考の余白が、少しずつ削られていきます。
ここでは、「どうして未来が見えにくくなるのか」を、
働くママに起きやすいリアルな視点から整理していきます。
⸻
1|目の前のタスクに反応し続けるだけで、1日が終わってしまうから
朝から会議、資料作成、メールの対応。
急ぎの依頼が入れば、気持ちの切り替えも必要になる。
気づけば “今日をどう乗り切るか” に意識の多くが向いていて、
未来に意識を向ける余裕がなくなってしまう。
この状態が続くと、
視野は自然と近い未来だけに固定されてしまいがちです。
⸻
2|“頑張ってなんとかする”ことが習慣化し、本音の願いが見えなくなるから
職場でも家庭でも、頼られることが多い。
「ここまでは自分がやったほうが早い」と思ってしまう。
優先順位を調整しながら、毎日をなんとか回していく。
この「頑張ってなんとかする」という姿勢は強みでもあるけれど、
続けていると “本当はどうしたいのか” が奥に押し込まれてしまう。
その本音が、すぐには手に取れない場所に隠れてしまうんです。
⸻
3|思考の“余白”がなくなり、未来を考えるスペースが消えてしまうから
未来を考えるうえで必要なのは、
まとまった時間よりも、ほんの数分の静かな余白。
ところが、忙しさが積み重なると、
その数分でさえも他のタスクに埋まってしまう。
今日をどうまわすかだけで頭がいっぱいになると、
未来を思い浮かべるスペースは自然と消えていく。
その結果、
今の延長線上にある未来しか描けなくなる。
⸻
4|周りの期待を優先し、自分の希望が後ろに下がってしまうから
職場の期待、家族の期待、子どもたちの期待。
大切にしたい人が多いほど、
つい自分の希望を後回しにしてしまう。
未来について考えるとき、本当に大切なのは
周りの期待ではなく、あなた自身の願い。
でも忙しさが続くと、
その願いの声がますます小さくなっていく。
⸻
5|不安や迷いが薄い膜をはり、未来の視界を曇らせてしまうから
仕事の負荷、家庭の状況、予測のつかない変化。
日々のストレスが積み重なると、
未来を見つめる視界にうっすらした膜がかかったように感じる。
「今の働き方を変えるのは少し怖い」
「自分にできるだろうか」
そんな気持ちが、未来のイメージをぼんやりさせてしまうのです。
⸻
未来が見えにくいのは、忙しい人に起きる“自然な反応”
ここまでの理由を振り返るとわかるように、
未来がぼんやりしてしまうのは、
あなたの能力の問題でも、怠けているからでもありません。
未来をもう一度取り戻すために必要なのは、
立ち止まって“棚卸し”をしてみることなんです。
⸻
第2章|今を見つめ、5年後を描き、1年後へ落とす “キャリアの棚卸し”
未来がぼんやりしているとき、
「先のことを考えなきゃ」と思っても、なかなか進まないものです。
そこで効果的なのが、
“現在 → 5年後 → 1年後” の順番で未来を描く棚卸し。
これはコーチングの現場でも、
まだ言葉にできていない気持ちが浮かび上がりやすく、
未来の輪郭が自然に整っていく流れです。
では、その3つのステップを一つずつ見ていきましょう。
⸻
1|まずは「いまの自分の働き方」を見える化する(現在地の棚卸し)
未来を描くために最初に必要なのは、
いま自分がどんな状態にいるのか を知ること。
現在地を丁寧に見つめるだけで、
未来が見えやすくなる土台が整います。
以下の問いに、思いつくまま書き出してみてください。
● いま、どんな仕事に一番時間を使っている?
業務量の偏りや負荷の実態が見えてきます。
● 家のことで、いま一番気がかりなことは?
家庭面での心の占有スペースが整理されます。
● どの仕事が “好き/前向き/自分らしさ” を感じられる?
エネルギーが湧く源泉に気づけます。
● 日常の中で「いちばん癒される瞬間」はどこ?
自分が自然体に戻れるポイントがわかります。
● どの作業が “疲れる/負荷が大きい” と感じる?
エネルギーを奪う要因が明確になります。
● 本当は、家庭と仕事のバランスをどれくらいにしたい?
“理想の配分”を言葉にすることで、方向性が整っていきます。
これらを書き出すだけで、
“いまの自分” がそっと輪郭を持ちはじめます。
⸻
2|次に、“5年後にはどうなっていたいか” を、のびのびと思い描いてみる(中期未来)
現在地が見えたら、
次は少し先の未来へ意識を向けてみましょう。
ここでは、
できるかどうかではなく、どうなっていたいか。
深く考えすぎず、
まずは“のびのび”と想像してみるくらいで大丈夫です。
以下の問いをヒントに、自由に未来を描いてみてください。
● 理想的だと感じる時間の配分は?
(仕事・家庭・自分時間のくらし方)
● 家庭の中で、どんな “母” や “妻” でありたい?
(役割の持ち方)
● プライベートで担っていたい役割はある?
(地域、趣味、学び、コミュニティなど)
● 仕事では、どんな分野や役割に興味がある?
(今の延長にこだわらなくていい)
● どれくらい「やりたい仕事」に時間を使えていれば納得感がある?
(働く満足度の軸)
● どんな状態で働いていたい?
(エネルギッシュ/自然体/マイペース など)
5年後という“少し先”は、
今の制限から自然と距離が生まれ、
まだ言葉になっていない気持ちが静かに浮かび上がる時間軸です。
⸻
3|そして、5年後に向けて「1年後の現実的なステップ」を考える(近い未来)
5年後の輪郭が見えてきたら、
次はその未来に向かうための 1年後の状態 を設定します。
1年後は、
“理想と現実をつなぐちょうどいい距離” です。
以下の問いが、未来を“行動可能な形”にしていく手助けになります。
● 1年後、毎日の時間の配分はどうなっている?
(朝・日中・夜・週末のリズムの変化)
● 家族の中で、どんな立ち位置になっている?
(役割・関係性・心の余裕)
● どんなコミュニティに所属している?
(職場以外の居場所・学びの場)
● 身につけたいスキルは、どんな形で習得を進めている?
(独学/講座/実務/ロールモデル など)
● チームの中で、自分らしさをどんなふうに発揮できている?
(強み・役割・関わり方)
● どれくらい“余白”をもって働けている?
(心の余裕・時間の自由度)
ここでは、
“やるべきこと”ではなく “どんな状態になっていたいか” を描くのがポイント。
状態が明確になると、
今日の小さな一歩が自然と見えるようになります。
⸻
“現在 → 5年後 → 1年後” が未来を見えやすくする理由
この順番は、
• 現在地を見つめて足元が安定する
• 5年後という“ちょっと先”で気持ちの輪郭が浮かび上がる
• 1年後で行動可能な未来へ落とし込める
という3つが自然に揃う流れです。
未来は、頑張って“ひねり出す”ものではなく、
見えるようになっていくもの。
そのための静かな土台づくりが、
この“棚卸し”なのです。
⸻
第3章|忙しいママほど「やりたい仕事」に挑戦すべき理由
働くママは、毎日いくつもの役割を同時に抱えています。
仕事を頑張りながら、
家族の時間も大切にしながら、
自分自身の気持ちとも向き合いながら。
どれも手を抜きたくないからこそ、
“自分のこと” が一番後回しになってしまうのは自然なことです。
でも実は、
忙しいママほど “やりたい仕事” を大切にすることが、
人生全体の充実感につながる。
ここでは、その理由を紐解いていきましょう。
⸻
1|“やりたい仕事”は、あなたのエネルギー源になるから
忙しさの中で真っ先に削られるのは、
「好き」「興味がある」「本当はやってみたい」という気持ちです。
でも、“やりたい仕事” は
心のエネルギーを静かに補ってくれます。
• やっていると自然と前向きになれる
• 自分らしさを感じられる
• 学びたい気持ちが湧いてくる
• もう少し頑張ろうと思える
こうした感覚は、
忙しい日々を支える 大切な栄養 になります。
だからこそ、やりたい仕事をゼロにしないことが大事なんです。
⸻
2|“やりたい仕事”は家庭の時間にも静かなプラスをもたらすから
「仕事を頑張ると家庭が犠牲になるのでは?」
と不安に思う人も多いですが、実際には違います。
ママ自身が満たされていると、家庭にもその余裕が伝わります。
• 家族との関わりに柔らかさが戻る
• 子どもへの声かけが穏やかになる
• パートナーとのコミュニケーションが円滑になる
• ちょっとした出来事に振り回されにくくなる
仕事と家庭の両方を大事にしたいからこそ、
“やりたい仕事” を大切にする価値があるんです。
⸻
3|“やりたい仕事”は、あなたのキャリアの軸を作ってくれるから
忙しい時期ほど、
キャリアは“今の延長線”で考えてしまいがちです。
でも、“やりたい仕事” には
あなたが未来に向かうための 方向性のヒント が隠れています。
• この分野に惹かれる
• この役割が心地いい
• この働き方が合っている
• このスキルをもっと深めたい
こうした小さな気づきの積み重ねが、
あなた自身の キャリアの軸 をつくっていきます。
そしてその軸が 明確にできていると、
迷ったときにも
「どちらを選べば自分らしさにつながるか」
が自然とわかるようになります。
⸻
4|“やりたい仕事”に挑戦することは、自分を大切にする行為だから
誰かの期待に応えることも大切です。
それは仕事だけでなく、家庭でもずっと続いている日常の営み。
でも、それだけだと多くの人は心をすり減らしてしまいます。
だからこそ、
「これは私が選んだ仕事だ」と思える時間を持つことは、
自分を静かに支える大切な土台になります。
• 私はチャレンジできている
• 私はやりたいことに取り組めている
• 私は自分の人生を、自分で動かしている
こうした感覚が、忙しいママにとって大きな安心になります。
“やりたい仕事” に挑戦することは、
自分を大切に扱う行為そのもの なのです。
⸻
“やりたい仕事”を小さく始めるだけで、未来は動き出す
挑戦といっても、
大きく動く必要はありません。
• 興味のある分野の人に話を聞いてみる
• 10分だけ調べてみる
• スキル学習のメモをつくる
• やりたい分野の小さな業務に “ちょっと手を挙げてみる”
未来は“小さな一歩”からしか動きません。
でもその一歩を踏み出せた瞬間から、
あなたの未来は静かに、確実に変わり始めます。
⸻
第4章|未来を動かす“最初の一歩”をつくる──小さな実践が道を拓く
未来を描いたあと、
いちばん多い声は「何から始めればいいかわからない」というものです。
でも、大事なのは“正解の一歩”ではなく、
いまの自分が動ける一番小さな一歩 をつくること。
ここでは、忙しい毎日の中でも無理なく未来を動かせる
行動の組み立て方 を紹介していきます。
⸻
1|“今日できること”をひとつだけ決める
未来を描くと、
必要なことが一気に見えて前のめりになりがちです。
でもそこで無理をすると、続きません。
最初に決めるのはただひとつ──
“今日できること”だけでOK。
• 5分だけリサーチする
• メモに一行だけ書く
• 気になる部署の人に声をかけてみる
• 明日の自分へのメモをひとつ用意する
たったこれだけでも、未来は静かに動き出します。
⸻
2|“頑張らなきゃ”に頼らず、自然に動ける仕組みをつくる
忙しいママにとって、
行動が続くかどうかは 仕組み が握っています。
“頑張らなきゃ”に頼らず、
自然に動ける仕組みをつくる。
たとえば…
• 子どもが寝た後の10分を「未来時間」にする
• スマホのホーム画面に“学びアプリ”を置く
• 朝のコーヒータイムに1ページだけ読む
• 在宅の日は始業前に10分だけメモする
“自然と動ける仕組み” がつくれると、
未来との距離はぐっと縮まります。
⸻
3|“やらなくてもいいこと”をひとつ減らす
未来に向かいたいのに動けないとき、
原因は “無意識の消耗” にあることが多いです。
• 他人のSNSを眺め続ける時間
• 断れない頼まれごと
• 自分を下げる考え方
• 完璧を求めすぎるクセ
こうした “やらなくてもいいこと” を
ひとつ減らすだけでも、
使えるエネルギーは驚くほど増えます。
未来への一歩は、
“やること” だけでなく
“やめること” からも生まれます。
⸻
4|半年後の自分に手紙を書いてみる
行動の方向性を整えるのにとても効果的なのが、
“半年後の自分に手紙を書く” という方法。
ちょうど現実味がありつつ、
しっかり未来にも意識が届く距離です。
手紙を書くときのヒントはこちら👇
• 半年前(いま)と比べて、何が変わっている?
• 半年後のあなたは、どんな気持ちで働いている?
• 半年前(いま)の自分に、どんな言葉をかけてあげたい?
• この半年間で、一番納得のいく選択は何?
未来の自分に語りかけることで、
“いまやるべきこと” が自然と浮かび上がってきます。
⸻
未来は“一気に変わる”のではなく、“積み重ねで変わる”
大きな変化は一瞬では起こりません。
未来は、
静かな一歩の積み重ねでしか動かない。
そしてその一歩は、
完璧である必要も、劇的である必要もありません。
大きな一歩じゃなくていい。
あなたらしい一歩でOK。
無理をしなくてもいい。
正解を選ばなくても大丈夫。
できることを、
できるタイミングで、
できる分だけ。
その積み重ねが、
あなたの未来をゆっくりと育てていきます。
⸻
第5章|未来は、いまの自分を大切にするところから始まる
ここまで読み進めてきたあなたは、
毎日の忙しさの中でも
「もっと自分らしく働きたい」
「未来の方向性を見直したい」
そんな静かな願いを抱えているのかもしれません。
そして、その気持ちをこうして言葉にしようとしている時点で、
未来はすでに少し動き始めています。
⸻
1|“いま”を大切にできる人だけが、未来を育てられる
未来を考えようとすると、
つい「変わらなきゃ」「もっと頑張らなきゃ」と
焦る気持ちが生まれがちです。
でも本当は、
いまの自分を丁寧に扱うこと が、
未来を育てるいちばんの近道。
• いま頑張れていること
• いま気になっていること
• いま大事にしたいもの
• いま心にある願い
そのすべてが、未来を形づくる材料です。
⸻
2|未来に向かう道は、誰かと比べなくていい
SNSや職場で見える“他の誰か”は、
どうしてもキラキラして見えるもの。
でも、あなたの未来は誰とも比べなくていい。
• 子育てのペース
• キャリアの進み方
• 心の余裕のつくり方
• 学びの時間のとり方
すべて “あなたの毎日とリズム” の中にあるもの。
未来のつくり方も、
あなた自身の速度で大丈夫です。
⸻
3|小さな一歩が、未来の景色を変えていく
棚卸しをすることも、
やりたい仕事を大事にすることも、
小さな行動から始めることも。
どれも特別な能力はいりません。
ただ、自分に優しく、
そして正直に向き合うだけ。
その小さな一歩が、
半年後・一年後のあなたの景色を変えていきます。
大きな一歩じゃなくていい。
あなたらしい一歩でOK。
⸻
4|未来は、あなたの言葉から育っていく
未来は、
一気に形になるものではありません。
でもあなたが書いた言葉、
あなたが描いた理想、
あなたが選んだ小さな行動が、
ゆっくりと未来をつくっていきます。
思い描いた未来は、
静かに、でも確実にあなたを導いていきます。
⸻
締めくくりのメッセージ
あなたは、いまの状況の中で
すでにたくさんのことを頑張っています。
そして、これまでの記事の中で描いてきた未来は、
決して遠すぎるものではありません。
忙しい毎日の中でも、
未来はいつからでも描き直せます。
どうか自分のペースで、
“あなたらしい未来” を育てていってください。