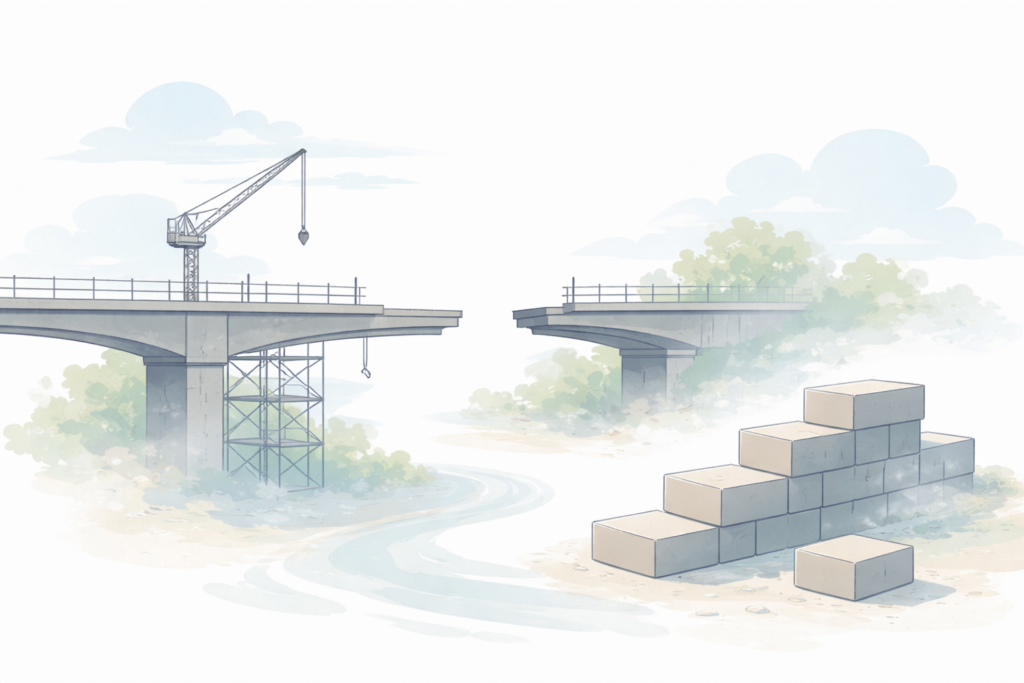1. はじめに|忙しさが減らない理由は、行動量の問題ではなかった
営業チームのリーダー層の方たちと話をしていると、
よく似た言葉を耳にすることがあります。
• もっと数字を上げないといけない
• クレーム対応に時間を取られている
• 人が育っていない気がする
どれも、現場に立っていれば自然と出てくる言葉ですし、
感覚としても間違っているわけではありません。
ただ、ぼくがコーチングをさせていただく時には、
これらを原因として深掘することはほとんどありません。
なぜなら、多くの場合、
クライアントさんが「問題だと思っているもの」は、
現象に近い位置にあることが多いからです。
数字が足りていない。
クレーム対応に追われている。
結果として、現場が忙しい。
ここまでは事実です。
ただ、この状態を
「行動量が足りていないのかもしれない」
「もっと動けば、なんとかなるはずだ」
と整理してしまうと、
結果として、さらに忙しくなる
一人ひとりは頑張っているのに、
さらに、やることは増えていく。
それなのに、
• 数字は上がらず
• クレーム対応も減らず
• 気持ちの余裕だけが削られていく
そんな循環に、
いつの間にか入ってしまうことがあります。
ぼくの場合、コーチングの場では、
渦中にいらっしゃるクライアントさんに、
少し距離を取って眺め直していただくような支援をすることが多いです。
あらためて、
チーム全体の現状を整理して言葉にするところから始めてみる。
すると、多くの場合、
クライアントさん自身が、
それまでとは少し違う視点で状況を捉え始めます。
ここで大切なのは、
その人が「本質的な原因」を
言葉として理解できているかどうかではありません。
必要なのは、
本質的に正しい選択と行動に辿り着くこと。
今回は、
そんな問いかけの積み重ねの中で見えてきた、
あるリーダーの気づきのお話です。
⸻
2. 数字とクレームというそれぞれの出来事
そのリーダーが最初に話してくれた内容も、
多くの現場でよく耳にする捉え方でした。
数字の話と、
クレームの話は、
それぞれ別の出来事として扱われているように感じました。
数字については、こんな整理です。
• 今期の目標に対して、数字が足りていない
• もっと「行動量」を増やす必要がある
• メンバー一人ひとりの動きが足りない
一方で、クレームについては、
また別の枠で語られていました。
• 確認不足や詰めの甘さが原因ではないか
• 経験の浅いメンバーが多い
• 注意や指摘を増やす必要がある
どちらも、間違った捉え方ではありません。
少なくとも、現場で起きていることを説明しようとすると、
自然とこういう言葉になります。
数字は、「行動量」の話。
クレームは、「対応」や「品質」の話。
それぞれを、
それぞれの出来事として扱い、
別々に対応を考えていく。
• 数字に対しては、「行動量」を増やす
• クレームに対しては、注意やチェックを強める
捉え方としては、ごく自然な流れです。
ただ、そのリーダー自身も、
話しながら、少しずつ違和感を口にし始めました。
「行動量」を増やすほど、
現場は忙しくなる。
忙しくなるほど、
確認やすり合わせの時間は減っていく。
その結果、
クレーム対応に時間を取られ、
また数字が遅れていく。
一つひとつの出来事は理解できるのに、
全体として眺めると、
どこか噛み合っていない感じが残る。
それぞれの出来事として扱えば扱うほど、
やることだけが増えていく。
その割に、
「これで本当に前に進んでいるのか」という手応えは薄い。
このあたりから、
「何かがズレている気がする」という感覚が、
言葉にならないまま残り始めていました。
⸻
3. 行動を増やしても、楽にならなかった理由
数字とクレームを、
それぞれ別の出来事として整理する。
この整理の仕方は、
多くの営業現場で、自然に選ばれやすいものです。
数字が足りていないのであれば、
まずは「行動量」を増やす。
クレームが起きているのであれば、
チェックや確認を強める。
どれも、
その場では納得感のある対応です。
実際、こうした整理のもとでは、
行動は着実に増えていきます。
• アポの数を増やす
• 動く時間を増やす
• チェックや確認の回数を増やす
• 指摘や声かけの頻度を上げる
一つひとつは、
どれも間違っていない取り組みです。
ただ、多くの場合、
行動が増えても、
気持ちはあまり楽になりません。
忙しさは続いている。
むしろ、以前よりも増している。
それなのに、
• 数字は思うように伸びず
• クレーム対応に追われる時間も減らない
そんな状態が続くことがあります。
ここでよく聞かれるのが、
こんな言葉です。
「これだけ動いているのに、
なぜ手応えがないんだろう」
行動は増えている。
でも、全体として前に進んでいる感じがしない。
一つひとつの出来事には対応しているのに、
流れとしては、
同じ場所をぐるぐる回っているような感覚が残る。
忙しさの中身が、
少しずつ変わっていないことに、
あとから気づくことも少なくありません。
• 目の前の対応に追われる
• その場を収める
• 次の対応に移る
この繰り返しが、
以前よりも速いペースで回っているだけではないか。
そんな違和感が、
はっきりとした言葉になる前に、
現場に残り続けます。
⸻
4. 見方が少しだけ変わる瞬間
行動を増やしても、
忙しさの質が変わらない。
そんな違和感を抱えたまま、
現場を眺め直してみると、
これまでとは少し違うものが目に入ってくることがあります。
数字とクレームを、
別々の出来事として整理しているとき。
視線は、
「どれだけ動いているか」
「どこでミスが起きたか」
といった、個々の出来事に向きがちです。
けれど、
一歩引いて全体を眺めてみると、
別の問いが立ち上がってきます。
「このチームは、
どんな流れで仕事をしているんだろう」
出来事の原因を見つけて対処するのではなく、
仕事がどう流れているかに目を向けてみる。
すると、
これまで別々だと思っていた出来事が、
少しずつつながって見え始めることがあります。
• 忙しさの中で、説明が省かれていないか
• 急いでいるがゆえに、確認の前提が揃っていないことはないか
• 「わかっているはず」という認識が、共有されないまま進んでいないか
ここで、
すぐに「答え」を出そうとしたくなるかもしれません。
ただ、ぼくの感覚で言うと、
この段階で「答え」を見つけようとする必要はありません。
それよりも、
• 行動量を増やすかどうか
• 注意や指摘を強めるかどうか
とは別の場所に、
考える余地があることに気づけているかどうか。
そのほうが、
ずっと大切だと感じています。
忙しさの原因を、
経験値や能力、意欲の問題にするのではなく、
仕事の流れや、やり取りの形として眺めてみる。
それだけで、
これまでとは少し違う選択肢が
視界に入ってくることがあります。
かと言って、
チームの状態をより良くするために必要なことが、
大きな改革や、新しい施策であるとは限りません。
まずは、
「この忙しさは、
どんな流れから生まれているんだろう」
そんな問いを、
チームの外からではなく、
中に置いてみること。
この問いを持てたとき、
現場の見え方は、
ほんの少しだけ変わり始めます。
次の章では、
この「見え方の変化」が、
どんな行動の選び方につながっていくのかを、
もう少し具体的に見ていきます。
⸻
5. やることを増やすのではなく、選び直しをする
見方が少しだけ変わると、
不思議なことに、
「何を足すか」よりも先に
「何を急がなくていいか」が見えてきます。
行動量を増やす。
チェックを強める。
指摘の回数を増やす。
そうした選択肢が、
一度すべて頭の中に並んだうえで、
あらためて問い直されます。
本当に、
今いちばん必要なのは何だろう。
その結果、
最初に選び直されるのは、
新しい施策ではありません。
むしろ、
• すぐに答えを出そうとしない
• その場で判断を急がない
• 「分かったつもり」で次に進まない
そんな、仕事の進め方そのものです。
たとえば、
何かが起きたとき、
すぐに原因を特定して対処するのではなく、
「今、どんな流れの中で起きているんだろう」と
一度立ち止まってみる。
メンバーに対しても、
「足りない点」を指摘する前に、
前提がどこまで共有されているのかを確かめてみる。
忙しいからこそ、
省いていた説明や確認を、
あえて省かずに置いてみる。
どれも、
目新しい取り組みではありません。
ただ、
先を急がずに選び直す
これまでとは違っています。
結果として、
すぐに数字が跳ね上がるわけでも、
クレームが一気に消えるわけでもありません。
それでも、
• やり直しのやり取りが減る
• 「それ、聞いていませんでした」が少なくなる
• その場しのぎの対応が減っていく
そんな小さな変化が、
少しずつ現れてきます。
忙しさそのものが、
いきなり消えるわけではありません。
ただ、
忙しさの中身が変わっていく。
この感覚が持てることは、
とても大きな意味を持ちます。
ここで大切なのは、
どんな時でもうまくいく正解や、
誰にでも当てはまる型を探す、という意味ではありません。
その都度、
• 今の流れの中で、何を足すか
• どこを急ぐか
を考えるのではなく、
• このチームにとって、今は何と向き合うタイミングなのか
• 今ある滞りは、どうすれば自然に流れるだろうか
を選び直していく。
そうした選び直しの積み重ねが、
結果として、
仕事を前に進めていきます。
次の章では、
この「選び直し」が、
リーダー自身の関わり方を
どう変えていくのかを見ていきます。
⸻
6. リーダーの役割が、少しだけ変わる
やることを増やすのではなく、
選び直しをしていく。
この感覚が少しずつ育ってくると、
リーダー自身の立ち位置にも、
小さな変化が生まれてきます。
これまでは、
• 判断を早く出すこと
• 正解を示すこと
• 前に引っ張ること
が、
リーダーの役割だと感じていたかもしれません。
けれど、
現場を丁寧に眺め直していく中で、
別の役割が見えてきます。
それは、
流れを整える役割です。
誰かを強く動かすのではなく、
止まっているものを無理に押すのでもない。
今、チームの中で起きていることを受け取りながら、
• 言葉は足りているか?
• 前提は共有されているか?
• 負荷のバランスは取れているか?
そんなふうに、
状態を確かめる問いを自分に投げかける。
結論を急ぎすぎず、
必要なところにだけ、
問いを置いていく。
「ここ、どう思う?」
「いま、何が一番やりづらい?」
「ここは、急がなくていいんじゃない?」
そんな一言が、
仕事の流れを少しずつ変えていくことがあります。
不思議なことに、
こうした関わり方に変わってくると、
リーダー自身が
すべてを背負っている感覚も、
少しずつ薄れていきます。
判断の重さを、
一人で抱え込まなくてよくなる。
正解を当てに行くのではなく、
チーム全体で
流れを確かめながら進めるようになる。
その結果として、
• 数字の追い方が変わり
• クレームへの向き合い方が変わり
• 忙しさの質が変わっていく
そんな変化が、
ゆっくりと起きていきます。
ここで大切なのは、
リーダーが「何かをうまくやる」ことではありません。
先を急がず、
今ある流れを丁寧に扱い、
必要なタイミングで問いを置く。
その積み重ねが、
チームの中に
自然な循環を生み出していきます。
数字が足りていない状態や
クレームの発生は、
別々に対処する問題ではなく、
チームの流れの中で起きている出来事です。
そう捉え直してみると、
リーダーの役割は、
「答えを出す人」から
「流れを整える人」へと、
少しだけ姿を変えます。
もし今、
• 忙しさが減らない
• 手応えが薄い
• 頑張っているのに、楽にならない
そんな感覚があるとしたら。
やることを増やす前に、
一度立ち止まって、
問いを置いてみてください。
今ある滞りは、
どうすれば自然に流れるだろうか。
その問いは、
チームだけでなく、
リーダー自身の在り方も、
静かに整えてくれるはずです。