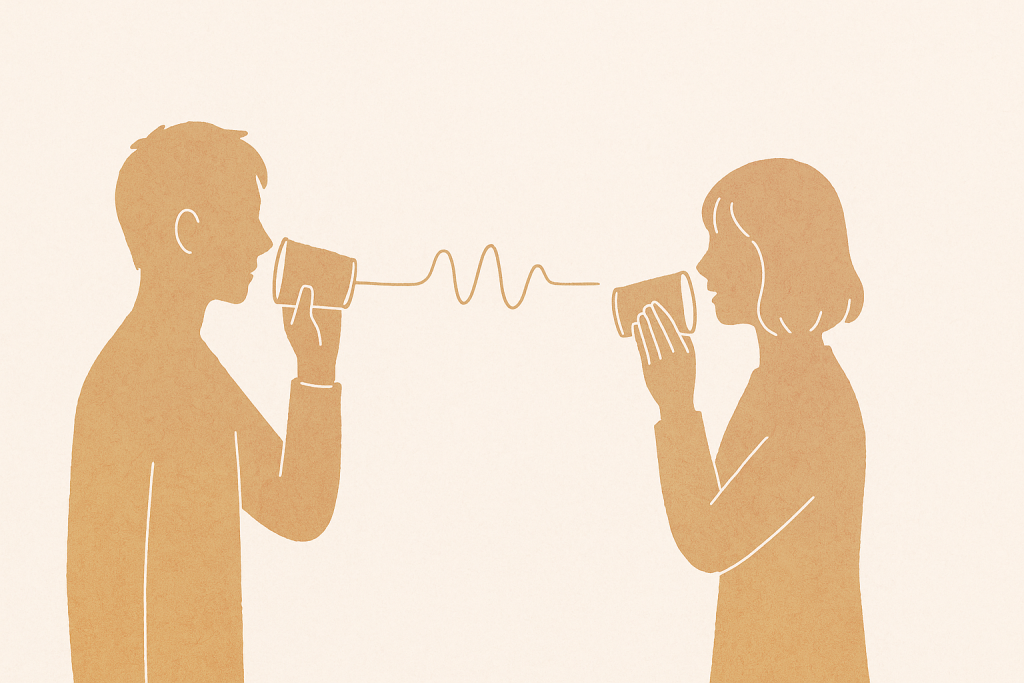「そんなつもりはない」これまでの自分の伝え方
あるコーチングセッションでのことです。
そのクライアントさんが、ふとこんなことをこぼしました。
「そんなにきつく言っているつもり、ないんですけど……」
この言葉が、どこか自分の胸にも引っかかりました。
というのも、これまでにも──特に、縦の関係性が色濃い組織でマネジメントに関わっている方たちとのコーチングセッションで、
同じような言い回しを何度か耳にしてきたからです。
「そんなつもりはなかった」。
でもその“つもり”が、人との関係性のなかでは、
ときに“圧”として伝わってしまうことがあります。
今回のセッションをきっかけに、こうした言葉が生まれる背景に、あらためて目が向きました。
コーチングの現場では、「圧が強いよね」と誰かに言われた経験について話をお聞きすることがあります。
それは、部下や後輩、あるいは上司との関係の中で出てきた言葉かもしれません。
そうしたやり取りを聴いていると、
「相手にきちんと覚えてほしい」「ちゃんとできるようになってほしい」
──そんな思いで接している方が多いと感じます。
けれど、そうした関わり方の裏には、
人との関係性を構築することへの不器用さ
でも、役割として“関わらなければならない”。
そのギャップの中で、伝え方が強くなってしまうことがあるのだと思います。
⸻
②|“伝え方”に幅を持たせるということ
これまでぼくが対話してきた「圧が強い」と言われがちな方たちは、
一人ひとりとても誠実で、責任感の強い方ばかりでした。
人に何かを教えるときも、任せるときも、
できるだけわかりやすく、丁寧に、きちんと。
抜けや誤解がないように、言葉を選び、説明を尽くす。
そんなふうに、関係性を大切にしようとしている姿を、何度も見てきました。
だからこそ、「なんで伝わらないんだろう?」と戸惑う気持ちになるのも、よくわかります。
でも、ときにその言葉や関わり方が、
相手にとっては「きつい」「重たい」と感じられてしまうことがあります。
伝える側がどれだけ丁寧でも、
受け取る側には「責められているように感じる」「詰められているように聞こえる」と
伝わってしまうことがあるんです。
それは「伝え方が強すぎる」というよりも、
**“伝え方にゆとりや幅を持たせる余地がある”**ということなのかもしれません。
「どの言葉が伝わりやすいのか」
「どのくらいの情報量でちょうどいいのか」
「どのタイミングで伝えるのが効果的なのか」
──そんな問いを持ちながら、
“伝え方”そのものを広げていくこと。
それは、伝える力をさらに磨くだけでなく、
相手との関係性をより深くするための、大切な一歩になると思うのです。
“距離感”を調整して相手に合わせる技術は、
伝える側が心にゆとりを持って、意識的に行わないと
うまくいかないことが多いように思います。
ただ、「きちんとやりたい」「丁寧に伝えたい」という思いがあるからこそ、
その“伝え方の幅”を少しずつ広げていくことで、
もっと自分らしく、相手と関われるようになるのではないか──
そんなふうに感じています。
⸻
③ 相手との間にある“ズレ”を自覚する
どんなに誠実に伝えても、「伝わらない」「響かない」というズレは、どこかで必ず生まれます。
たとえば──
言葉を尽くして伝えたつもりなのに、相手の表情は冴えない。
問いかけたはずなのに、「うーん…」と口ごもったり、黙り込まれてしまう。
こんなふうに、相手の反応が薄いときこそ、
「なんで伝わらないんだろう」
「もっとちゃんと話すべきだったかも」
と、自分の“伝え方”を強めてしまう。
でも、実はこれが悪循環の始まりであることも多い。
そして、ときには周りからのフィードバックで、ようやく
「ああ、そういうふうに伝わっていたのか」
と気づくことになるのです。
こうした“ズレ”を認識することができれば、
自分の伝え方にどんな「前提」や「思い込み」があったのか、
それに気づくきっかけとして活かしていけるようになるはずです。
だからこそ、「伝えたこと」と「伝わったこと」の間にある“ズレ”に、
すこしずつ意識を向けられるようになること。
それが、自分らしい伝え方の精度を上げていく土台になるのではないでしょうか。
⸻
④ 相手を動かすのは、言葉の量より“距離感の設計”
誠実に、真剣に、丁寧に──
相手に伝わるようにと、言葉を尽くす。
それ自体は悪いことではありません。けれども、
言葉の“量”や“強さ”で関係を動かそうとするほど、かえって相手の心が遠ざかることもあります。
たとえば、何度も念押しをしたり、繰り返し確認したり、強い言葉を使ったり。
あるいは、「わかってほしい」という気持ちが強くなりすぎて、
知らず知らずのうちに、相手の思考や感情のスペースを奪ってしまう──。
そんなことも、少なくないのではないでしょうか。
大切なのは、「どれだけ言うか」や「強い言葉で伝えること」ではなく、
「どんな距離で関わるか」という感覚です。
それは、“近づきすぎない”ということではなく、
相手のペースやタイミングに寄り添える、余白ある関係性。
つまり、「踏み込みすぎず、離れすぎず」という“距離感の設計”のようなものです。
もちろん、言葉は関係を築くための大切な手段です。
でも、それだけでは足りないこともある。
ときには、「あえて言わない」ことや「ちょっと待つ」ことが、
信頼をつくる助けになることもあるはずです。
“伝え方”を磨こうとするのと同じくらい、
“関わり方”の距離感に意識を向けること。
それが、相手を動かす静かな力になっていくのではないでしょうか。
⸻
⑤ 関係性を選びなおすための「3つの見直しポイント」
相手を動かす「距離感の設計」と言っても、
感覚だけに頼るのは難しいこともあります。
そんなときは、次のような観点から
関わり方を見直してみると、ヒントが見えてくるかもしれません。
1|“近づきすぎていないか”を見直す
• 相手の成果や成長に、過剰に責任を感じていないか?
• 「わかってほしい」「変わってほしい」という気持ちが強くなりすぎていないか?
→ 一歩引くことで、相手との関係を健全に保ちやすくなります。
2|“離れすぎていないか”を見直す
• 言わなくても伝わるだろう、と放置していないか?
• 無関心やあきらめが距離をつくっていないか?
→ あらためて伝えてみることで、想像以上に関係が動くこともあります。
3|“お互いの立場や状態”を見直す
• いま相手はどんな状況にいて、何に余裕がないのか?
• 自分の立場や発言が、どう受け取られている可能性があるか?
→ 状況の変化に合わせて関わり方を選ぶことは、信頼を保つカギになります。
これら3つの見直しを実践することで、完璧ではなくとも「距離感の再設計」をする事ができます。
⸻
⑥「関わり方」は、選び直せる
「そんなつもりじゃなかったのに」──
意図していない伝わり方に気がついた時に、
多くの人が抱くのは、“誤解された”という戸惑いや、“うまくできない”という落ち込みです。
けれど、人との関係性は、
一度つくったら終わりではなく、何度でも選び直すことができるものです。
「こうすれば伝わるはず」と思っていた関わり方も、
相手の状況や自分の立場が変われば、かえって負担になってしまうことがあります。
逆に、以前は届かなかった言葉が、タイミング次第でスッと入ることもある。
だからこそ大切なのは、
言葉の“量”や“強さ”を変えることよりも、関わり方を“見直す”視点を持ち続けること。
・近づきすぎていないか
・離れすぎていないか
・相手との「今」をちゃんと見ているか
この3つの問いかけを通して、自分のスタンスを少しずつ調整していくことで、
たとえすぐに関係が改善されなかったとしても、
「自分にできる関わり方」を丁寧に選び取っていくことができます。
完璧じゃなくていい。
でも、自分の意志で関わり方を整えていけるという実感は、
きっとあなたの人間関係に、静かな安心感をもたらしてくれるはずです。
小さな見直しの積み重ねが、やがて大きな信頼につながっていきます。